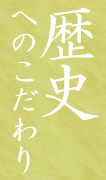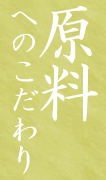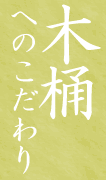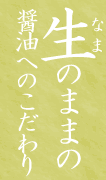| |
江戸から明治にかけての土浦は野田、銚子と共に関東の醤油の三大名醸地と称されていました。土浦藩主土屋政直侯は、藩内で収穫される良質の大豆と小麦に着目し、藩の有力な商品として醤油醸造を奨励し販売させました。当時ぜいたく品であった醤油は江戸幕府老中を務める土屋侯の後押しを得て江戸に販路を拓きました。
 醤油のことを「御下地 おしたじ」(広辞苑 第2版)ともいうのは常陸の国(現在の茨城県)で生産された醤油が美味しく評判がよかったので「常陸(ひたち)の国の醤油」、「お常陸 おひたち」が転化したものと言われています。「お常陸」の品名は当時「ひたちのもの」と呼ばれて珍重されていた土浦の醤油にこだわって名付けました。 醤油のことを「御下地 おしたじ」(広辞苑 第2版)ともいうのは常陸の国(現在の茨城県)で生産された醤油が美味しく評判がよかったので「常陸(ひたち)の国の醤油」、「お常陸 おひたち」が転化したものと言われています。「お常陸」の品名は当時「ひたちのもの」と呼ばれて珍重されていた土浦の醤油にこだわって名付けました。 |
|
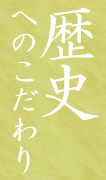 |
|
| |
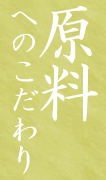 |
| 醤油は大豆、小麦、塩を原料とする醗酵食品です。材料がシンプルなだけに原料選びと醗酵課程の管理が重要です。「お常陸」は厳選した茨城県産のみの大豆と小麦を使用。塩は自然塩「伯方の塩」を選びました。それ以外には何も加えないで、現存する明治初期の藏の諸味用木桶で約1年かけてゆっくり熟成させることで、「お常陸」のやわらかな色、すっきりとした味、ふくよかな香りが生まれます。 |
 |
|
|
混ぜ合わされた原料に麹菌が加わってできた醤油の素である諸味(もろみ)は、「お常陸」専用蔵の専用木桶で1年以上ゆっくり寝かされます。蔵の木桶の中では原料に加えた麹菌だけでなく、もともと蔵と木桶に棲みついていた様々の菌達が忙しく働き出します。
 その時人間は細心の注意を払って見守りながらそっと彼らが働きやすいよう環境作りに励みます。「お常陸」醸造用に使用している木桶は明治時代初期のもの。蔵も含めて当時の建物と木桶をそのまま使用しています。古い蔵と木桶を毎日使用しながら維持管理することは努力が要りますが、柴沼醤油ではこうしたことを、物を伝えるのではなくそこに棲む醤油造りに関わる生き物(菌)を伝えることと考えています。 その時人間は細心の注意を払って見守りながらそっと彼らが働きやすいよう環境作りに励みます。「お常陸」醸造用に使用している木桶は明治時代初期のもの。蔵も含めて当時の建物と木桶をそのまま使用しています。古い蔵と木桶を毎日使用しながら維持管理することは努力が要りますが、柴沼醤油ではこうしたことを、物を伝えるのではなくそこに棲む醤油造りに関わる生き物(菌)を伝えることと考えています。 |
|
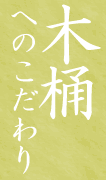 |
|
| |
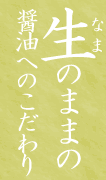 |
醤油は塩分があるので調味料として保存性は良い部類にはいります。しかし通常市販されている醤油は容器に充填する前に加熱殺菌(85℃)します。加熱殺菌すると保存性は良くなりますが色が濃くなり香りも本来のその生醤油がもつ香りと比較すると変化します。
 原料にこだわり醸造工程に徹底的にこだわった「お常陸」は、加熱殺菌の方法は取らずにセラミック濾過による除菌処理の方法を選びました。更にクリーンブースを設置した専用充填室での充填など除菌への徹底したこだわりが、諸味から搾った生醤油そのままの香りと色と味をお客様にお届けすることを可能にしました。 原料にこだわり醸造工程に徹底的にこだわった「お常陸」は、加熱殺菌の方法は取らずにセラミック濾過による除菌処理の方法を選びました。更にクリーンブースを設置した専用充填室での充填など除菌への徹底したこだわりが、諸味から搾った生醤油そのままの香りと色と味をお客様にお届けすることを可能にしました。 |
|
|
| |
| Copyright (C) 2006-2013 Shibanuma-syouyu
Co., Ltd. All rights reserved. |
 |